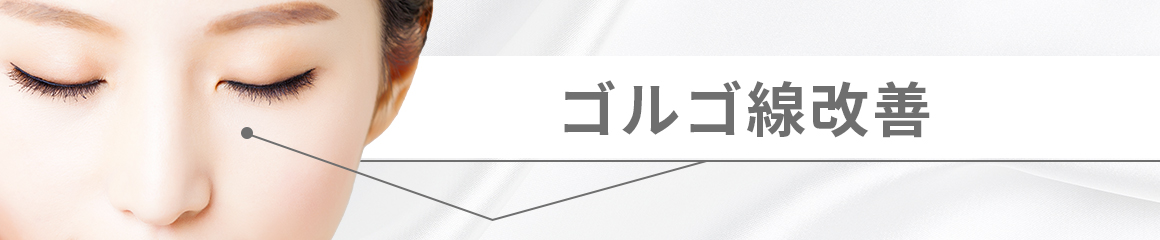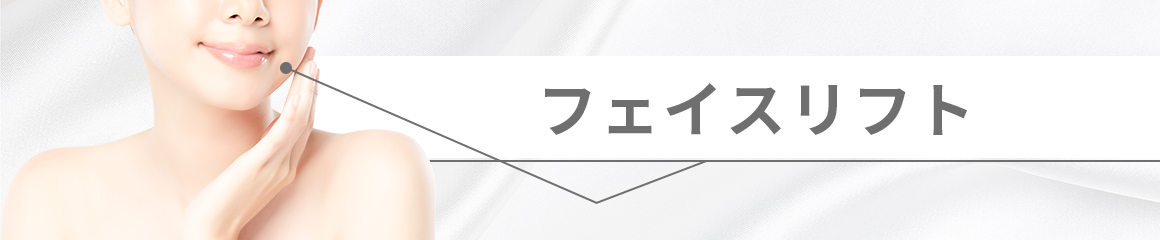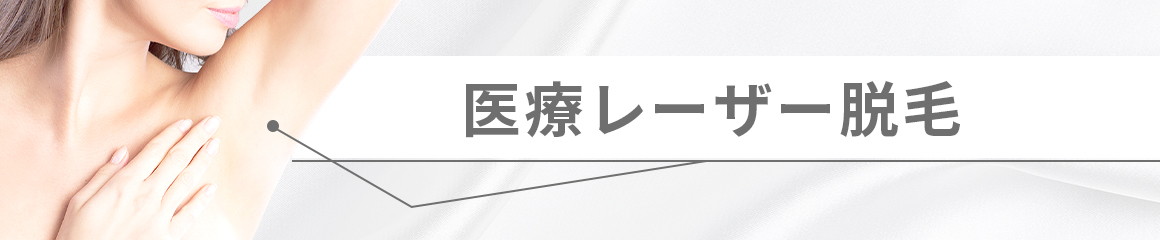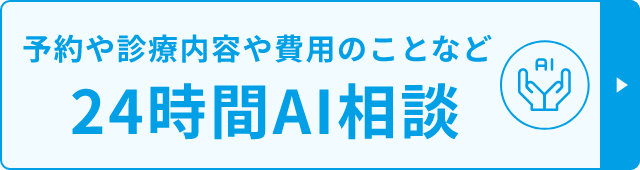本誌独占インタビューノーベル経済学者は指摘するポール・クルーグマン「1ドル100円超え、アベよ、これでいいのだ」
「週刊現代」2013年2月16・23日号より
戦争しなければ大丈夫
いま安倍晋三首相が推し進める経済政策・アベノミクスに批判の声が聞こえ始めている。その代表的なものが大胆な金融緩和をすると「ハイパーインフレ(急激なインフレ)」になってしまうというものだが、まったく的外れだ。
日本と同じように金融緩和をしているここ米国でも、実はハイパーインフレの恐怖が数年前から語られ続けてきた。しかし、現実を見ればハイパーインフレが起こっていないことは誰もが知るところだ。
さらに、私はアベノミクスが唱えられ始めてからのマーケットの動向を見ているが、日本の期待インフレ率はちょうどよい値で推移している。いままで市場が日本の物価についてデフレ予測を続けていたことを考えれば、いまは少しのインフレ期待があることで、むしろ経済にとってプラスに働いている状況になっているのだ。
ポール・クルーグマン。2008年にノーベル経済学賞を受賞した経済学の泰斗。プリンストン大学教授を務め、米ニューヨーク・タイムズ紙に寄稿するコラムがマーケットを動かすと言われるほどの影響力を持つ。
そんな氏がこのほど本誌の独占インタビューに応じた。続けてこう語る。
もちろん私だって、万が一ハイパーインフレになれば、国民が苦痛を味わうことになるという点に関して異論はない。しかし、日本では大きな戦争でもやらない限り、ハイパーインフレにはならないということは認識しておいたほうがいい。
さらにアベノミクスで大規模な財政出動をやると財政悪化につながるという批判もあるが、これも現実をきちんと見ていない批判といえるだろう。
どうしてか。それは安倍首相が大規模な財政出動を唱えても、日本の長期金利は1%未満の水準を超えておらず、政府の借り入れコストはほとんど変化していないことからよくわかる。一方で、先ほど述べたようにインフレ期待は高まっているのだから、むしろ政府の債務は実質的に減っていることになる。日本の財政見通しは、悪くなるというよりむしろ、大きく改善しているのだ。
ギリシャのように国債危機に陥るのではないかと不安視する向きもある。しかし、ギリシャは独自の通貨を持たない国であり、日本とはまったく違う。
仮に日本の財政問題が危ないとマーケットが判断した際にも、そのときは金利が上がるのではなく、通貨「円」が売られ、円安が進むというシナリオが起こるだけだ。円安になるのは、果たして日本経済にとって悪いことだろうか。
安倍首相の経済政策を、樽に入った豆腐を配るような「利益誘導型」の古い経済政策に戻ったと批判する者もいる。しかし、日本をデフレから脱却させるために必要なのは、何にカネを使うかということよりもどれだけカネを使うか—つまりこれは、質より量の問題なのである。
世界の常識を覆す
日本は過去20年にわたりすでに多額の公共投資を行ってきたが、日本経済が前進する兆しが見えると、すぐに急ブレーキをかけてきた。財務大臣が出てきて、「借金の懸念がある」と言って財政出動を抑えてしまうのだ。
日本銀行も金融緩和—つまり紙幣を多く刷ること—によってデフレ退治をすべく立ち向かおうとしたが、ここでも同じく、少しでも経済が回復し始めると、緩和の手を緩める方向に舵を切った。紙幣をばら撒きすぎると、急激なインフレの恐れが出てくると言ってきたのだ。
さらに、財政刺激策をやる際には金融面でのサポートがなく、金融緩和をやる際には財政面でのサポートがない。日本の政策当局はいつもそんなことを繰り返し、自らの手で、経済が持続的に改善するという望みを潰してきた。結果、長くデフレから脱却することができず、国民は苦しみ続けてきたのだ。そしてこれは、欧米を含めた世界の先進国にも同じことがいえる。
しかし、昨年末に再登板した安倍首相は、こうしたいままでの世界の政策当局がやってきたのとはまったく違う政策を唱えている。なんとしても経済の長期低迷を終わらせるという決意をもって、金融・財政両面で大胆な政策を打ち出しているのだ。
私はこのアベノミクスを評価している。これこそが日本がデフレから脱却するために必要な処方箋となりうると思っているからだ。そしてこれが成功を収めれば、日本が先進国の中で先んじて、経済低迷から脱する方法を示すことになるだろう。もちろんそれは、世界の経済政策担当者が過去20年間信じてきた原則が間違っていたことが証明される時の訪れも意味するのだ。
アベノミクスの恩恵はすでに日本経済にもたらされている。いままでデフレが続くと予想していたマーケットが考え方を変え、インフレを期待する方向へと転換を始めているからだ。
つまり、いま日本では名目金利が大きく動かない中で、インフレ期待が高まっている。それは実質金利が下がることを意味し、実質金利低下の噦副産物器としてすでに日本で起きているのが「円安・株高」である。これが日本経済にとって非常に多くの恩恵を与えている。
たとえば日本の製造業。多くの日本企業はいまだに国内にhub(拠点)を置き、製品を輸出する態勢を取っているので、円が安くなればそれが輸出増を牽引することになる。
かつて日本が圧倒的な地位を誇っていたモノづくりの技術力に対して、アジア諸国などがキャッチアップしているのは確かだろうが—ちなみに私は、サムスンの携帯電話を使っている—日本企業がかつて持っていた多くの噦技術的創造性器は、円高などの悪いマクロ経済要因によって妨害されてきた面が否めない。
アベノミクスによる円安で日本の製造業が強さを取り戻すきっかけをつかめるようになるだろう。
さらに、実質金利が下がってくると、企業の設備投資などが活性化されることになる。特に金利に敏感な国内投資—住宅、建設などがその一例だ—は盛り上がりを見通せるといえる。日本はこれから労働人口が減っていく人口減少社会に突入するから停滞一色だといわれてきたが、アベノミクスによって経済成長が期待できるようになってきたというわけだ。
ではこの円安はどこまで行くのか。私は1ドル=100円を超える可能性があると思っている。さらに対ユーロで見ても、円はいまよりさらに安くなるだろう。なぜなら、ユーロ圏は日本と違って緊縮策を余儀なくされているからだ。米国もある意味で日本と同じような政策—小型版アベノミクスといってもいいだろう—を実行していることから、円と同様にドルもユーロに対しては安くなるだろう。
日銀総裁は外国人がいい
もし私が安倍氏のアドバイザーに指名されたら、アベノミクスをより効果的にするためにどんな提言をするか? それは興味深い質問だ。
まず言えることは、安倍氏が唱えている財政刺激策は、私から見ればそれでもまだ少し弱いということだ。もちろんインフラ投資についてはこれ以上の水準にするのは難しいだろうから、たとえば一時的な減税策などでいいので、刺激策の噦最初の一打器をもっと強化したらいいと思う。
金融政策については、日銀の噦心変わり器は大歓迎である。ただ、10年間の期待インフレ率はいま1%ほどであり、これを2%まで押し上げる必要がある。その意味で、日銀はもう少し何にコミットするかを正式に発表することが必要だろう。
インフレターゲットの目標を「2%」以上にする必要性を説くものもいるが、その必要性はない。
私もかつては「4%」と言っていたが、当時ほど日本の貯蓄率は高くないし、今回は金融緩和と合わせて財政刺激策も行われるのだから、そこまで高いインフレターゲットを設定しなくてもいい。2%で十分だし、いままでの日本の政策を考えればかなりの進歩だともいえる。
私はいま、あることを期待している。日銀がイギリスの中央銀行がやったのと同じことをする、つまり、イギリスがカナダ人を中央銀行の次期総裁として登用するように、日本も外国人を選択してみたらどうかということだ。
日本がもし外圧なくしてそれを実行したら、市場のマインドセットはガラリと変わり、日本経済に本当の変化が起きるだろう。
たとえ、外国人にできないとしても、
日銀総裁には学者を選ぶのがいいだろう。いままでの世界経済の歴史からいうと、政策に劇的な変化をもたらしたい場合は、中央銀行総裁に学者を使うのがいいと考えられるからだ。ちなみにいえば、米国のFRB(連邦準備制度理事会)議長であるバーナンキもイングランド銀行現総裁のマーヴィン・キングも学者である。
繰り返すようだが、安倍氏が唱えている政策は、日本がデフレの罠から脱却するためにまさに必要な政策である。残された問題は、いまはまだ唱えられている段階の政策が実際に実行された際に、十分に強力であることを維持できているかどうかだ。内容は正しくても、いざ実行に移す際に見かけ倒しに終われば、人々の期待感は一気に消えてしまうだろう。
私はアベノミクスがうまくいくことを望んでいる。日本のためにも、そして世界各国にとってのロールモデルとしても。
「週刊現代」2013年2月16・23日号より
ポール・クルーグマンは2008年のノーベル経済学賞の受賞者です。
日本にもたくさん経済学通の方はいらっしゃると思いますが、
“それは違うでしょう”
といえる実績と理論をお持ちの方はそうはいないと思います。
僕が少し気になったのは
日本と同じように金融緩和をしているここ米国でも、実はハイパーインフレの恐怖が数年前から語られ続けてきた。
ってところくらいです。アメリカはこの3年で日本よりも格段に強力な金融緩和してますからね。
あと、ポール・クルーグマンのいう外国人って、ご本人??だったらいいなぁって(笑)
或いは学者っていうのはいま、内閣官房参与を務めている浜田 宏一イェール大学名誉教授を念頭にしてるんですかね。
ただし年齢が76歳ですので少しそこが気になります。
湘南高校出身というのがなんとなく親近感が持てます。(弟の出身校なので)